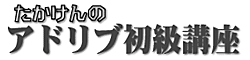
【秘伝その8:2番目のコードの意味じゃ】

Dm7 FM7
ダイアトニック・コード群の2番目の和音であるDm7は、その構成音からFM7の代理コードとして考えられていました。
Dm7(D,F,A,C) FM7(F,A,C,E)
そしてトニック、ドミナント、サブドミナントを使った一番変化に富んだ響きの流れを演出する際に、FM7の代わりに頻繁に使われるようになった、という説明です。
| 元の進行 | CM7 → | FM7 → | G7 → | CM7 |
| 意味 | (T) | (SD) | (D) | (T) |
| 変化した進行 | CM7 → | Dm7 → | G7 → | CM7 |
しかしこれでは今日やたらとセットのように使われるⅡ-Ⅴ(ツー・ファイブ)と言われる進行が、全てサブドミナント-ドミナントの進行であるという事になってしまいます。かつての音楽においては実際にそうだったのかも知れませんが、今ではもうちょっと納得しやすい別の説明もあります。
それはドミナントのG7というコードをさらに上部方向に発展させた場合に発生してくるテンション・ノートといわれる音の存在です。しかもこのG7のナチュラル(変化させない)テンション・ノートは、Dm7の響きと同じものになります。
(chord+ 9th,11th)
G7(G,B,D,F,+ A, C, )
Dm7( D,F, A, C, )
つまりドミナントは強い力を持っているために、いきなり流れの中に登場するよりも、前もって導入するサウンドを鳴らしておいた方が、より流れがスムーズになるという考え方です。
このアイデアを採用すれば、従来のドミナント・コードであった場所は全て2度マイナー7thのコードをセットのように前もって鳴らして、流れをスムーズに、より変化に富むようにさせることが出来ます。
(T) → (SD) → (T) → (D) → (T)
CM7 FM7 CM7 G7 CM7
↓
CM7 FM7 CM7 Dm7 G7 CM7
ここまでのダイトニック・コードの役割についての説明はお分かり頂けましたでしょうか。これは音楽の響きの流れについての、一番基礎的な部分ですが、同時に極めて西洋音楽的でもあります。実際のジャズにおける各コードの意味を読み取るためには、もうひとつの重要な要素である「アメリカ黒人が持つ、旋律に対する独自の傾向」、すなわちブルーノートについて触れなければなりません。
実際に使われるコードは西洋音楽の和声的理論と、アメリカ黒人が生み出したと言われるブルーノートが混在した結果、使われるようになったものがほとんどだからです。またこれがジャズらしさを生み出すようにもなっています。では次回はブルーノートの説明をします。